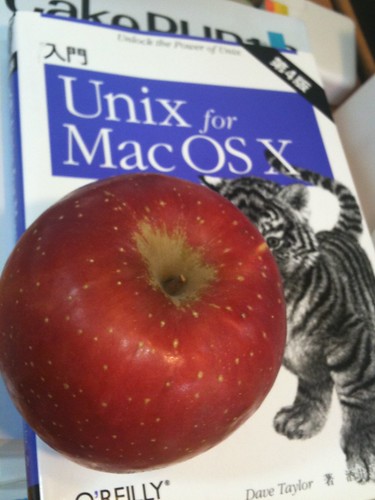先週用事があって福岡に行ったんですけど、Twitterで知り合った方に OSTERIA Fridge というレストランに連れて行ってもらいました。カウンターの席に座り目の前で料理を作ってるのを眺めながら食事しましたが、大変おいしかったです。料理について質問するとお店の人がとても楽しそうに説明してくれるので、なんかこっちまで楽しくなってきた。こういうお店は大変良いと思います。僕はジャンクフードとか学食のカレーとかが好きだし全然グルメ野郎ではないのだけど、また行ってみたいと思えるお店でした。時間の都合でデザートとコーヒーを注文できなかったことが残念でした。
Mephistoで技術ブログをやることにした
なんかTwitterで「最近のポータルシット変わったよね…」とかいう意見を目にするようになったので、パソコンネタだけ隔離して別にブログを始めることにした。使っているCMSはMephisto。Railsの勉強になるかと思って。早速DreamhostへMephistoをインストールしていて躓いてしまったのでちょこっとメモ。
とりあえず tech.portalshit.net というサブドメインを用意し、DreamhostのパネルでPassengerのセットアップ。その後SSHでサーバーに接続し、
$ git clone git://github.com/emk/mephisto.git
``
してgithubからプロジェクトをclone。
Mephistoのインストールにはいくつかgemが必要。Dreamhostには結構たくさんgemがインストールしてあるんだけど、いくつか足りないものがあった。とりあえず設置ディレクトリのルートで
```sh
$ rake gems:installと打ってみたところ、nokogiriとそれに依存するbrynary-webratが入らなかった。原因を調べてみたところ、xsltのライブラリをダウンロードして、gem install するときにパスを指定してあげる必要があるらしい。xsltのライブラリ自体はPHP5をカスタムインストールしたときに入れてあるので、以下のオプションでインストールした。
$ gem install nokogiri \n --with-xslt-include=/home/morygonzalez/php5/include/ \n --with-xslt-lib=/home/morygonzalez/php5/lib/無事インストール成功。その後もう一回 rake gems:install を実行してbrynary-webratも入り、管理ページにアクセスしてみると今度はPassengerのエラーが。これは単純にdatabase.ymlに development: のDB環境しか記述していなかったこと、 rake db:bootstrap のときに RAILS_ENV=production をつけていなかったことが原因だった。そういうわけでdatabase.ymlに production: の設定(sqlite3を使用)を書き、
$ rake db:bootstrap RAILS_ENV=productionですべてのインストール作業完了。いまこうして動いております。
今後はここにCakePHPやRails、JavaScript関連のことを書いていこうと思います。できれば一日一ポスト、その日に学んだことを書いていきたいです。
しあわせの隠れ場所
しあわせの隠れ場所
評価 : ★★★★☆
あらすじ
家庭崩壊してる貧しい黒人の少年マイケル・オアーが、裕福な白人家庭に養子として迎え入れられ、アメフト選手として大成する話。マイケルが一時的に身を寄せていた自動車整備工場のおっさんが、自分の子どもをカトリックの名門校に入れるために、「マイケルをアメフト選手にしたら将来有望だぜ。だからうちの息子と一緒に入学させてくれよ」と高校のアメフト部のコーチに持ちかけるところから話が始まる。しかし白人だらけの高校にうまくなじめず、下宿先のおばさんにも疎まれマイケルは肩身の狭い思いをする。寒い冬の夜に半袖短パンで路頭に迷っているところに通りかかったリー・アン・テューイ(サンドラ・ブロック)が見かねて家に泊めてあげるところから話は進んでいく。実話がベースらしいです。
ベタな感動作品だけどとても良かったです。『きみに読む物語』とか『私の中のあなた』的な良さがあります。金持ちな白人が貧しい人を助けるっていう話だと偽善っぽさが出てくるんだけど、サンドラ・ブロックが肝っ玉母さんを好演してて、偽善っぽさがあまり漂ってないです。
ぐっと来るのがマイケルが遠慮するところ。サンドラ・ブロックは最初マイケルを家に泊めたときに警戒するんだけど、朝起きてみるとマイケルは礼儀正しくてきれいにふとんをたたんでひっそり屋敷を出ていこうとする。テューイ家で暮らすようになってからも、サンドラ・ブロックのことをミセス・テューイって呼んで「そういうよそよそしい呼び方はやめなさい」って注意されたり。お互いが手探りでじわじわと心の距離を詰めていくところが良かったです。
サンドラ・ブロックが金持ち奥さん達とのランチで、黒人や貧しい地区に住む人たちのことを馬鹿にする連中に向かって "Shame on you" って言うシーンはさすがにやり過ぎというか偽善なオーラが漂ってたけど、最初はマイケルのことを馬鹿にしてた高校のアメフト部のコーチも、試合で白人の審判がマイケルに不利な判定をしたときに「この人種差別野郎!」と食ってかかるところなど、周囲の白人たちの意識が変わっていく感じがさわやかでした。
裕福な白人が貧しいマイノリティーを助ける映画では、去年『路上のソリスト』を見たんだけど、あれは金持ち白人のオナニーストーリーという感じであまりさわやかさがなかった。しかしこの映画はマイケルも白人達も一緒に成長して家族になっていくという一体感があって、そこが良かったのではないかと思います。サンドラ・ブロックの行動力あふれる感じもプラスに作用。
蛇足になるけど、僕が陰ながらいいなぁと思ったのが、一家の大黒柱ショーン・テューイ。リー・アンに黙って、高校にマイケルの緊急連絡先をテューイ家にするなど頼りになるパパぶりが男前でした。やっぱ男は金だなーと見ながら思った。扉をたたく人という映画で、チュニジアからの移民のために大学教授が手をつくすのを見ても思ったけど、人生には金がないとどうにもならない局面がたしかにあって、そういうときにさらっと金を出せるのが男のかっこよさだなと思った。僕もあと15年後くらいにはそういう金を持ったかっこいいおっさんになっていたいです。
Linuxのブート中にキーボードをがちゃがちゃやると危ない
Linux(CentOS 5.4)がずーっと起動しっぱなしだったので、たまにはリブートするかと
sudo rebootかけた。普段、サーバーにはモニターもキーボードもつないでいないので、このままだと「キーボードがないわよ」みたいな警告が出てブートが途中で止まる。たいていキーボードをつけてがちゃがちゃやると「キーボード発見しました」みたいな表示が出てブートが進むので、モニターはつながず、キーボードだけつないでがちゃがちゃやっていた。しかし…。
ブラウザーからサーバーにアクセスしてもつながらない。あれ? sshでMacBookからサーバーに入り、
/etc/init.d/httpd configtestしてみると
httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/conf.d/ruby.conf: Cannot load /etc/httpd/modules/mod_ruby.so into server: /etc/httpd/modules/mod_ruby.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission deniedとか出る。えー? mod_ruby.so が読み込めないのかー。mod_rubyを再インストールしたり httpd.conf を書き直してみたりしたんだけど効果なし。同じエラーで困ってる人いないかと、「mod_ruby centos エラー」とかでググってみたんだけど、そういう人は見つからず。キーワードを変えて「cannot restore segment prot after reloc: Permission denied」でググってたら以下のサイトにたどり着いた。
なるほどそういうことか。どうやらモニターにつながずキーボードをがちゃがちゃしていたときに /etc/selinux/config の設定を変更してしまっていたみたい。(SELinuxの小技)
結局、 /etc/selinux/config を編集して
SELINUX=disabledとして無事Apacheが起動できるようになった。
午前中の時間が無為に過ぎて行ってしまった…。
読書スタイル
今日は読書の方法について書いてみます。自分の読書方法をオススメするわけではなくて、他の人の読書方法を知りたいという意図のもと、まずは自分の読書方法を開陳してみる次第です。だめ出しとか突っ込みとかさらにいけてる読書方法があったら教えて欲しいです。
付箋を貼ってる

ここ一年くらいの習慣ですが、読書をするときには重要だと思える箇所や気になった箇所に付箋をつけるようにしています。読書といっても小説は含みません。ここでいう読書とは新書など少し堅めの本を読むことを指します。
本に線は引きたくない
本に直接線を引く人もいます。しかし僕はそれは気が進まない。理由は貧乏性だからで、いつかその本を売るかもしれない。線が引いてあると買い取り拒否されるかもしれない。付箋なら売るときはがせばいいので問題なしなわけです。(といはいえ読まなくなった本を売ったことはないんだけど)
売る売らないは別にしても、誰かに貸したりあげたりしたときのことを考えると、何となく本には線を引きづらいです。特にハードカバーの本には線が引きづらい。ソフトカバーのいわゆる学校の教科書的な本や問題集などにはためらわずに線を引きます。売ることもないしこの手の本はどんどん情報が古くなっていく消費財だから。しかしハードカバーの本は自分の所有物でも簡単に何かを書き加えてはいけないような緊張感があります。
話がずれました。そういうわけで僕は線を引くかわりに付箋を使ってます。
三色ボールペンメソッド
本に線を引く方法で知っているものに斎藤孝さんの三色ボールペンメソッドがあります。「重要」、「とても重要」、「個人的に面白かった」の三種類で色を使い分けるやり方です。
理想的なのは本の内容に沿って色を使い分ける方法でしょう。テーマAについては赤、Bについては青、Cについては黄、といった具合で色を使い分けておくと、後から読み直すときに非常に内容を把握しやすい。
しかしこれはあくまで理想論で、本を頭から読んでいる段階でその本の中に何種類のテーマがあるのかを把握し色を用意していくのは困難。結局三色くらいで、重要度や自分が受けた印象に合わせて色を使い分けるのが現実的なマーキングのあり方でしょう。
付箋の貼り方

僕が使っている付箋は住友スリーエムの『ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し』です。プラスチック製のケースに入っていていて、ティッシュみたいな仕組みでぺりぺりと交互に調子よくめくれるところが気に入ってます。下半分は透明になっているので本文の上に貼っても内容が見えなくなることはありません。カラフルな色バリエーションもいい。
しかしながら色が多すぎるのは否めない。6色もあります。3色くらいがベストですね。6色のなかの特定3色だけ用途を決めて使えば良いんだけど、貧乏性なのでついつい6色満遍なく使ってしまう。その結果、折角色つきの付箋を使っているのに色を見ただけで意味を理解できないという非常に残念なことになっております。貧乏性の馬鹿野郎。
読んでいて重要だと思った箇所や個人的に面白かった箇所に付箋を貼りながら読んでいき、読み終わったらブログに感想を書く前にもう一度付箋が貼ってある箇所を拾い読みします。この作業でだいたい本の内容が頭に入ります。
今後の課題としては、もっと付箋の色を抑えて、それぞれの色に特定の意味を持たせてそれを定着させる必要があります。
中途半端な感じですが以上が僕の読書スタイルです。よかったらみなさんの読書スタイルを教えて欲しいです。
UnixとしてのMac OS X
MacはUnixとして使うと便利
Macはシャレオツパソコンとして使うだけじゃもったいない。一応UnixなのでUnixとしても使える。
Unixコマンドが気持ちいい
-
「○×は使用中のため削除できません」とか警告が出るファイルも
sudo rm -f <ファイル名>と打てば消せる。ストレスフリー。 -
10分後にシャットダウンさせるとかも楽ちん
出かけなきゃいけないけどまだDropboxの同期が終わってなくて電源落とせない、みたいなときは、
sudo shutdown -h +nとか打つとn分後にシャットダウンする。nのところに10を入れて実行すれば10分後にシャットダウンする。便利。
きっかけ
GitやVim、サーバー環境構築などでTerminal.appを多用するようになった。
-
Git
- とにかく便利。プログラミングしてなくても、htmlやcssのバージョン管理もできる。『入門git』という本を読んでるけど、著者はこの本自体をGitを使ってバージョン管理しながら書いたらしい。ちょっとUnixの操作に慣れれば劇的に快適な文書のバージョン管理環境がゲットできる。共同作業で使うんじゃなく一人でやるんでも便利。
-
Vim
- 最初はとっつきにくかったけど、慣れたらとても使いやすい。さすがにhtml書くときはグラフィカルなエディターを使うけど(Espressoで全裸コーディングとか)、プログラムを書くときはvimの割合が増えた。Terminalとの行ったり来たりが楽だし、そもそもGitを使ってたら
git commit -aのときにVimが自動で開くし必然的に使う機会が増える。
- 最初はとっつきにくかったけど、慣れたらとても使いやすい。さすがにhtml書くときはグラフィカルなエディターを使うけど(Espressoで全裸コーディングとか)、プログラムを書くときはvimの割合が増えた。Terminalとの行ったり来たりが楽だし、そもそもGitを使ってたら
MacPortsは神
MacPortsのリポジトリは結構頻繁に更新されてる。新しいバージョンをインストールするために自分でリポジトリ追加したりしなくていいし、とにかくパッケージ管理が楽。個人的に自宅サーバーやるんだったら古いMacにMacPortsで環境つくる。
というわけで
iTunesとSafari専用マシンとしてだけMacを使うのはもったいないです。良かったらUnixとしても使ってあげてください。
Snow LeopardになってもUnixとしてのOS Xには大きな変化がないので以下の本がオススメです。僕も毎日拾い読みしてます。
いろんなところで紹介されてるSnippetsってSnippetのパクリなんじゃないの?
TUAWなんかでも紹介されてるSnippets、思いっきりSnippetのパクリじゃないですか? アプリケーションの名前からして単数形か複数形かの違い。アプリケーションのURLも完全に誤認を狙ってるような一字違い。Snippetの方が http://www.snippetapp.com/ で、Snippetsの方が http://www.snippetsapp.com/ 。ただしSnippetの方は別のサイトにリダイレクトされるけど。アイコンもなんか似てるし。


Snippetの開発元のFuel Collectiveの人はわりと怒っちゃってるみたい。
Fuel Collectiveのサイトにはこんなリボンかかってる。

で、肝心のソフトの中身ですけど、SnippetsはCode Collector ProとSnippetを足して二で割ったような感じかなと思いました。control + sで呼び出せて近未来的なルック&フィール(One, Two, Three, Four)のSnippet(後発じゃない方。紛らわしい)の方が好きかな。サポートにメール送ったら親切に返事くれたし。Fuel Collective、がんばって欲しいです。