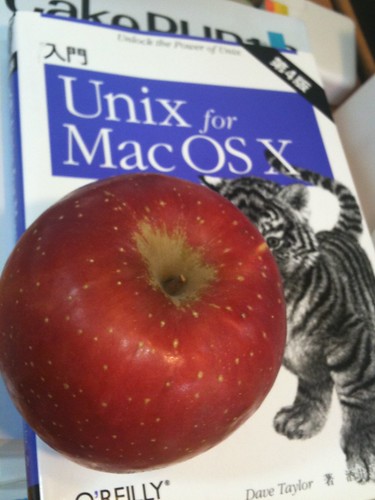この前大阪で第二回アメ村ブルゾンの会をやったんですけど、そこで日夜ネットストーキングプログラミングにいそしんでおられる皆さんとお会いして、TwitterのStreaming APIの使い方を教えてもらいました。なんか自分でやろうとしてたんだけど、全然見当違いなところを見ていたみたいで、僕もStreaming APIでネットストーキングできるようになりました。pokutunaさんにもらったコードと "Twitter Streaming APIをRubyで試してみる - しばそんノート":http://d.hatena.ne.jp/shibason/20090816/1250405491 を参考に、以下のような感じにしてみました。
#!/usr/bin/env ruby
# coding: utf-8
require 'net/http'
require 'uri'
require 'rubygems'
require 'json'
USERNAME = 'morygonzalez'
PASSWORD = '***'
uri = URI.parse('http://chirpstream.twitter.com/2b/user.json')
begin
Net::HTTP.start(uri.host, uri.port) do |http|
request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
request.basic_auth(USERNAME, PASSWORD)
http.request(request) do |response|
raise 'Response is not chunked' unless response.chunked?
response.read_body do |chunk|
#空行は無視
status = JSON.parse(chunk) rescue next
#eventを含まないものは無視
next unless status['event']
source = status['source']
if status['target_object']
target_obj = status['target_object']
target_user = target_obj['user']
puts "#{status['event']}: #{source['screen_name']} -> #{target_user['screen_name']}: #{target_obj['text']}"
elsif status['target']
target = status['target']
puts "#{status['event']}: #{source['screen_name']} -> #{target['screen_name']}"
end
end
end
end
rescue Timeout::Error => ex
p "<-----!!!! Timeout::Error!!!!----->"
retry
end教えてもらったコードではTweetの内容を垂れ流しにするやつだったんですけど、自分でちょこっといじってTweet以外のステータスを表示するようにしてみた。しかしなんか調子悪いっぽくて、完全にはStreamを取れてないっぽいです。
でもまぁ一歩前進したことは確か。Rubyがんばるぜ。