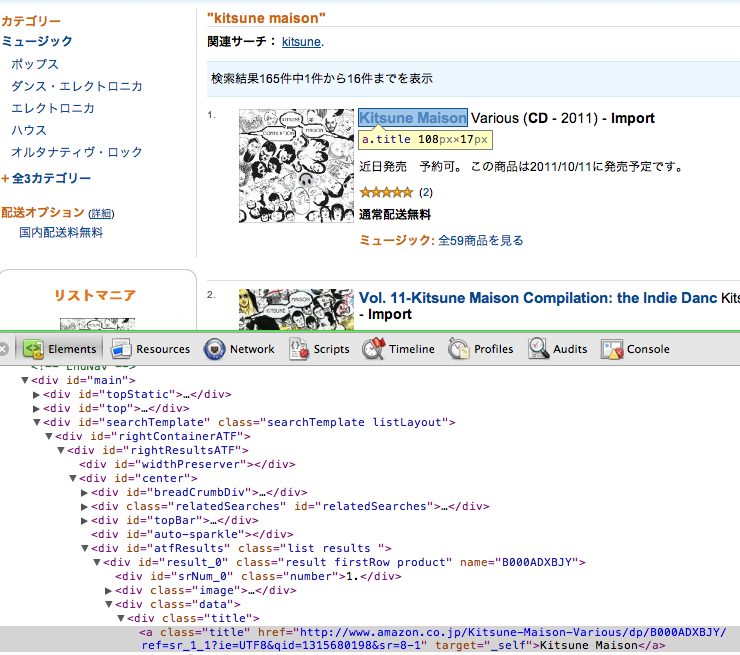転職したお祝いに、ワイフにMacBook Airを買ってもらった。シャレオツ気取りでUS配列キーボードをビックカメラで注文した。なんでビックカメラで注文したかというとYahoo! BB光開通キャンペーンでもらった二万円分のビックカメラ商品券があったからだ。CTOは基本的にApple Storeのみで可能だが、ビックカメラ店舗内のApple ShopだとCTOを受け付けているという情報をネットで入手していた。
購入時には「CTO注文の場合キャンセルはできません、二週間程度お時間をいただきます、JISモデルならすぐお持ち帰りいただけますが本当によろしいですか?」と三回くらい聞かれたけど「いいです」と言ってUS配列モデルを注文した。そしたらもうそろそろ一ヶ月になるのにまだ届かない。
やはり俺のようなダサ坊がUS配列のMacになんて手を出すべきではなかったのだ。おとなしくJIS配列キーボードモデルを購入していれば、今頃Airを携えてドトール天神新天町店などで無限インターネットしたりできていたのに。ちょっとシャレオツを気取ってUS配列を注文したばかりにこんなことになった。
そもそもUS配列を使っていいのは原則的に値引きなしのApple StoreでMacを買える金持ちだけなのだ。これまで一度たりとも定価でMacを買ったことがない俺のような賤民がUS配列に手を出すべきではなかったのだ。商品券を使って意地でも値引きされた金額でMacBook Airを買おうとしたがためにこのような事態に至ったのだ。
さらに悲しいことに、5000円値引きするからと同時加入したイーモバイルのGP02についても、GMOくまポン経由で買うとsshも使えるアドバンスドプランを月額2990円で契約できたらしい。俺は月々3880円で契約してしまった。どうせ3880円払うならソフトバンクのULTRA WiFiとかにしておけばよかったと激しく後悔している。ULTRA WiFiはイーモバとソフトバンクのハイブリッドモデルなので、両方の回線を自動的に切り替えて通信できる。イーモバは田舎では全然電波の感度がよくない。ソフトバンクも悪いけど、イーモバイルよりかはましだ。
きっとApple StoreでUS配列のMacBook Airを買うようなリッチメンは情報収集も万全で、月額利用料3880円でGP02を契約した俺を尻目に、GMOくまポンを使って入手した月額利用料2990円のGP02とUS配列のMacBook Airを駆使して美女とのデートで利用する遊園地やレストランやバーやラブホテルを検索したりしているのだ。あるいはネット証券でデイトレーディングを行い、さらに富を増幅させているかもしれない。俺との差は開いていくばかりだ。