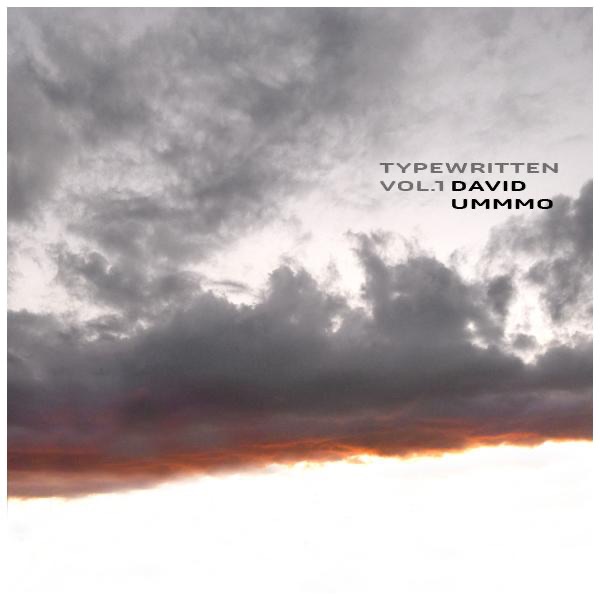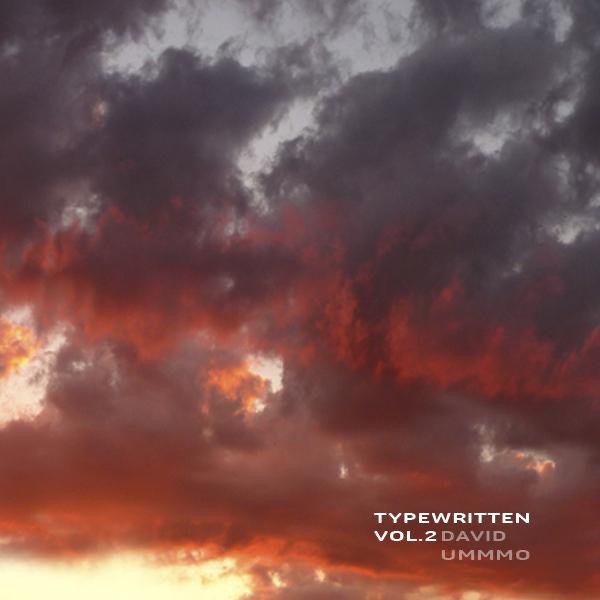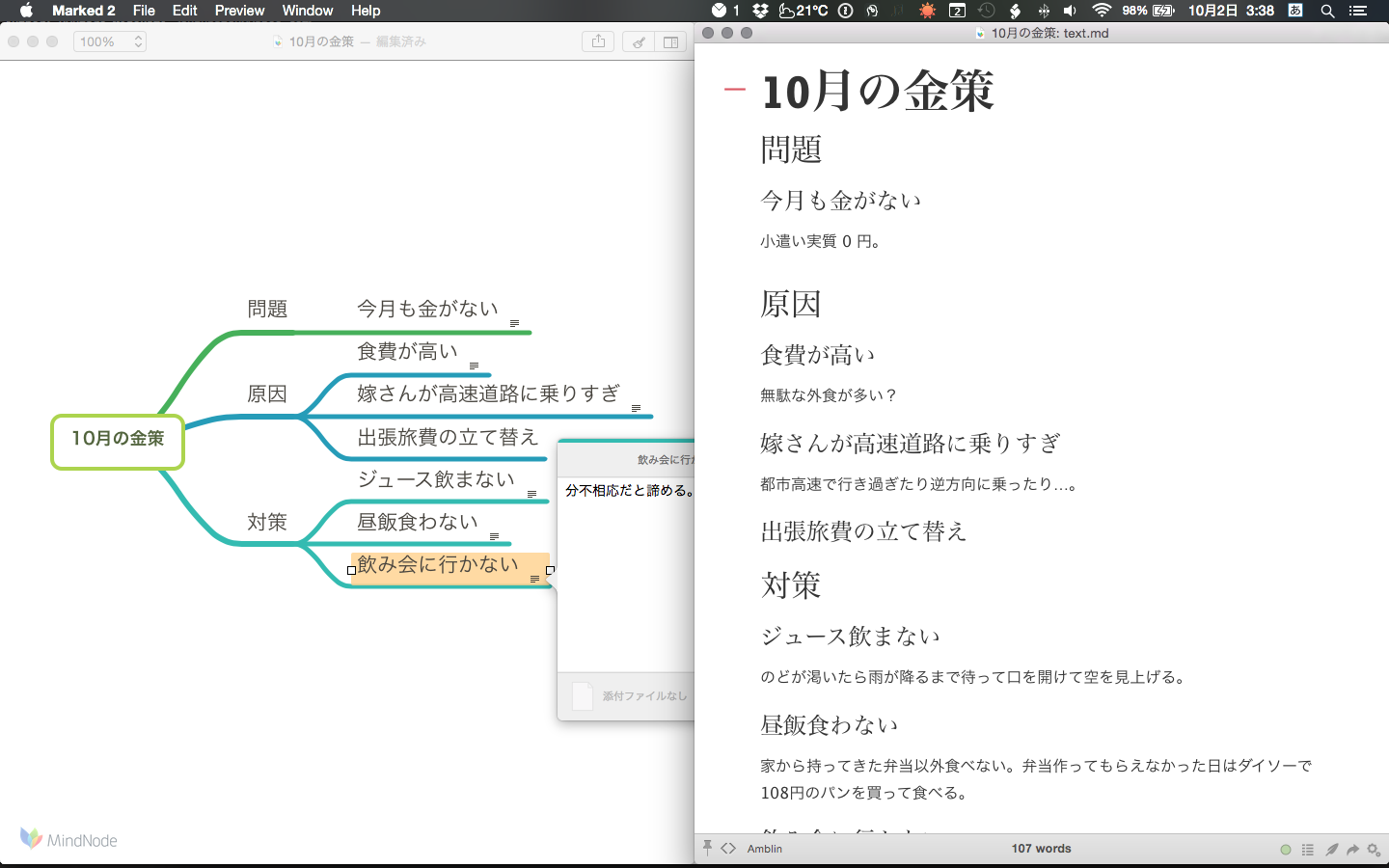この記事は地方在住ITエンジニア(元・地方在住も可) Advent Calendar 2015 - Adventar 6 日目の記事です。地方在住ウェブエンジニアの著者が思ったことを書きます。
自己紹介
熊本出身で大学生の頃は東京に住んでいました。いまは福岡市に住んでいて、東京のインターネット企業に雇ってもらってます。リモートで仕事してます。
福岡のことを書かない理由
最初は福岡での暮らしについて書こうかと思ったのですけど、福岡在住の著名 IT エンジニアはきしだなおきさんや新井俊一さんなど以前からたくさんいらっしゃって情報発信しておられますし、最近では前職でご一緒させていただいた、昼に寿司を食べた舌が乾かないうちに夜焼肉を食べたりしている金満エンジニアで、天気の話からでも HashiCorp プロダクトの話に結びつけるうずづらさんや、女性ファン急増中のプラチナ貴公子スーパー Go lang プログラマーモノクロメガネさんなど雨後の竹の子のようにいて情報発信しておられますし、また福岡について書いたら最終的に「福岡便利ですよ、移住してみませんか」みたいな結論になりがちですし、加えてほかの皆さんの記事を読む限り福岡は地方には含まれなさそうなので、福岡にやってくる前に住んでいた熊本県阿蘇地方での生活を綴りたいと思います。
キャリアの始まり
僕が最初ウェブ開発を生業にしたのは熊本県の過疎地域、阿蘇地方でした。元々学生時代にコンピューターサイエンスを学んでいたわけではありませんでしたし、プログラミングというより HTML マークアップと雑用担当としてウェブ開発業界に潜り込みました。
地方のつらみ
ギャラが少ないことと勉強会に参加できないことがつらかったです。
ギャラが安い
実家暮らしだったので何とか生活できていましたが、年収200万に満たなかったです。地方にもインターネット関係の仕事がないわけではないのですけど、まともな賃金が支払われる仕事がないと感じます。地方でのシステム開発は、自治体が都会の SI 会社に発注する数千万円から数億円規模の仕事か、商店のホームページのアクセスカンター設置みたいなやつしかなくて、後者に対する報酬はとても少ない。一年と少ししか働いていませんでしたが、このまま歳をとるとやばいな、という危機感はありました。
勉強会に参加できない
田舎にいると勉強会的なものに一切参加できないのもつらかったです。勉強会がしばしば開催されている福岡に引っ越してきて何度か勉強会に参加してみたけれど、勉強会は参加するだけでは無意味で発表する側にならないと得られるものが少ない、ということがわかって勉強会渇望症みたいのはなくなりました。いまにして思えば隣の芝生は青い状態なだけだったという感じがあると思います。勉強会とかなくても学ぼうと思えば学べるはずです。ただし勉強会で発表しまくって目立ちたいとかそういう人は都会に住んでないとダメでしょうね。
相談できる相手がいない
職場に質問・相談できる相手がいないのが心細かったです。常に一人で考えて試行錯誤を重ねる必要がありました。それはそれで良い経験にはなっていたと思うけど、知っている人がいてヒントを出してもらいながらステップアップしていく方が断然効率的だったと思います。もし『情熱プログラマー』でいわれるところの師匠なような存在がいたら、今頃もっとよいエンジニアなれていたのではないかと自らの怠慢を棚に上げ思います。
街の灯火が遠い
ほかの人の記事を読むと通勤時間が長いと書いてる人が多いですけど、当時の職場は家から車で 10 分のところにあったので通勤時間に関しては不満はなかったです。この辺はたまたまが職場が家から近くてラッキーだっただけだと思います。ただ仕事のあとに映画を見たいとか本を買いたいと思っても、田舎過ぎて仕事帰りに何かするというのが無理だった(そもそも仕事が終わるのも遅かった)のはつらかったです。
田舎にいて良かったこと
自然
当時の職場が森の中にあって、職場から阿蘇山の景色を望むことができました。また昼休みに職場の周りを散策すると、小川があったり農家に引かれて道を歩いてる牛とすれ違ったりして毎日がちょっとしたハイキングみたいでした。疲れたときに窓から阿蘇の山々を眺めると癒やされましたし、毎日昼に散歩すると頭がすっきりする感覚があってよかったです。キャリアのスタート段階だった、独身で時間を自由に使うことができた等様々要因はありますが、当時はよく学ぶことができていたなという感じがして、これら自然環境が少なからずよい影響を与えていると思います。
無双
ギャラが少ない一方で上司が非技術者なのでやりたい放題できるというメリットがありました。課題に対して自分の好きなとおりに解決策を考えて解答を出すことができました。以前、社内 SE は無双できると書かれている記事を読みましたが、まさにそんな感じです。信頼さえ得てしまえば無双できると思います。
結論
- 莫大な遺産があって働かないでも食っていける
- スタートアップで働いていたが上場してストックオプションで億単位の金融資産を得た
- 独身、あるいは妻子に逃げられて養うべき家族がいない(慰謝料とか養育費も払わなくてよい)
等々で収入が多くなくてもかまわないなら、田舎で仕事するのも良いのではないか、と思います。特にキャリアのスタート期を終えて一定程度のスキルを身につけている状態で、働き口さえあれば、地方に引っ込んでもそれなりに楽しくやっていけるのではないでしょうか。ただし地方に引っ込んでも最新技術へのキャッチアップを怠らないことなど、意識を高く持つことは大事だと思います。
勤務先を地方に求めず、リモートで東京の仕事を請け負う、というやり方もありますが、東京の会社に雇用されて福岡でリモートワークしている僕個人の考えでは、リモートワークというのはやはりなかなか難しくて(リモートワークアドベントカレンダーで書こうと思います)、特に業務委託などでフリーランスの人が仕事を受けながら働くのは、受け手が相当の熟達者か、発注者と受け手が元同僚であるとかでないとディスコミュニケーションが発生してお互いつらい気がします。正規従業員として雇用されている僕も月一回程度東京に行って、膝をつきあわせて仕事しています。
役所が都市部のハイエナ SIer に発注するような仕事以外にも、地方在住のエンジニアがローカルビジネスのオーナーから請け負って価値を提供できるような場所はあるのではないかと思っています。以前田舎で働いていたときに、もう少し自分にスキルがあってお客さんにも意欲があれば、もっとウェブ技術を使って便利にできるのになぁと思うことがしばしばありました。ウェブサービス作ってユーザーめっちゃ増やしてドカーンだけがエンジニアリングの使いどころではないと思いますし、地方出身者が都市部に吸い寄せられていくだけでは先祖代々の墓は誰が守れば良いのか分かりません。何年先になるか分かりませんが、隙あらば地元に帰って何かしてみたいです。
跋文
最後に福岡で働くことについて一言書いておきますが、福岡はブラック企業が多い街という印象を受けます。街がコンパクトで皆歩いて帰れる範囲に住んでいるせいか、終電の概念が崩壊しており、平気で午前 2 時、 3 時まで働いている会社があります。なので福岡最高、福岡便利、福岡手榴弾!!、!などといった甘言に惑わされず、移住を検討する際にはまともな勤め先を確保した上で断行してください。僕は福岡で最初に働いた会社が本当にひどかったです。以上です。
この記事は地方在住ITエンジニア(元・地方在住も可) Advent Calendar 2015 - Adventar の 6 日目の記事でした(一日遅れて書いてます)。今日の担当は飲み会後、歩いて帰れる距離でも必ずタクシー帰宅をキメる @h_demon さんです。お楽しみに。