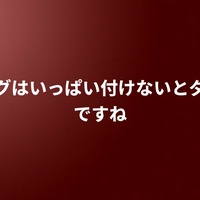去年( 2019 年)の年末、今年行ったところアドベントカレンダーに登録したが、いろんなアドベントカレンダーに登録しすぎて記事を書くことができなかった。 11 月に入って 2020 年のアドベントカレンダーの募集が始まったみたいなので、今年のシーズンが始まる前に去年のやり残しを片付けておきたくなった。ということで 11 ヶ月遅れで「今年行ったところ」です。
2019 年に行ったところでは 10 月に訪れた平戸が一番心に残っている。このときは平戸を訪れることが目的だったのではなく、平戸の手前、旧田平町にある中瀬草原キャンプ場1でのキャンプが目的で、キャンプに行ったついでで平戸の街に偶発的に立ち寄った。昼過ぎにテントを片付けて腹が減っていたし、このまま帰るのはもったいない(福岡から平戸までは車で 3 時間近くかかり、一泊キャンプしただけで帰るのはガソリン代や移動時間のコストパフォーマンスが悪い)と思われ、気まぐれで訪れたにもかかわらず、平戸の街は強く印象に残っている。

平戸は島であり、平戸に入るには平戸大橋を渡る必要がある。平戸大橋の下には田平港があって、昔は船で海を渡っていたようだ。平戸を訪れたあとに読んだ司馬遼太郎の『街道をゆく 肥前の諸街道』では渡し船に乗っていた。
平戸の街に入り、平戸港交流広場に車を停めた。 2 時間までは駐車料金が無料だった。ここは港であると同時に観光案内所(とても綺麗なトイレがある)でもあり、観光スポット情報を集めた。
平戸にはオランダ商館(オランダ商館の跡地に建物が復元され資料館になっている)と松浦歴史資料館(旧平戸藩主松浦氏2から寄贈された松浦氏の私邸を資料館に改装したもの)、ザビエル記念教会がある。時間的に遅く全部回ることはできなそうだったので、まずはザビエル記念教会、その後オランダ商館に行くことにした。

ザビエル記念教会
ザビエル記念教会は丘の上に建っている。おもしろいことにこの教会に辿り着くまでの坂道にはお寺がたくさん建っており、寺町を通り抜けて坂を登り切ると教会が建っているという不思議な空間になっている。教会からは竹林越しに平戸城が見える。



教会のあとは平戸の街を通り抜け、オランダ商館を訪れた。

オランダ商館

オランダ商館は復元された建物だ。平戸が貿易港として栄えていた頃に商館は作られたが、 1640 年に幕府の意向により貿易はすべて長崎の出島に集約されることになり、商館は破壊された。破風に西暦の年が書かれていることをキリスト教に警戒感の強い幕府から咎められたと言われているが、多分こじつけで、貿易の果実を松浦氏に独占させたくなかったのかもしれない。長崎ならば天領で、貿易の利益を幕府のものにすることができる。
商館には帆船の模型や松浦家が所有していた西洋の甲冑のほか、オランダ商館の家財や、当時貿易されていた品(器や香辛料など)が展示されている。商館の建物自体の構造も解説されていて、木造建築技術しかなかった 400 年前にいかにして貿易品を貯蔵するための巨大な貯蔵庫を建築したのかや、二階の窓から物品を積み下ろしするための巻上機(リフト)の構造を知ることができる。またオランダ人と結婚した日本人や、オランダ人との間に生まれた子どもがインドネシアに追放され、ジャカルタから「日本が恋しい」と綴って日本に送った手紙(ジャガタラ文)の展示もある。




商館は平戸瀬戸を見渡せる町外れにあり、平戸城や平戸の街を一望できる。平戸大橋も綺麗に見える。


商館近くには荷物の積み下ろしに使われていた埠頭が残っている。埠頭といっても簡易な石造の階段で、こんな小さな石段を介して歴史を動かす交易が行われていたのかと思うと感慨深かった。

商館自体は復元された建物だが、商館および商館員たちが暮らした居留地と市街の間には漆喰塗りの壁が現存している。オランダ塀と呼ばれていて、防火や市民の視線を避けるために作られていたものらしい。

長崎の出島同様、オランダ商館は市街から隔絶されていたのかもしれない。長崎の街もだいぶコンパクトだが、平戸はさらに街が狭く、平戸城はもちろんのこと、町中の至る高台から商館を見ることができる。街がコンパクトなため、壁で隔てられていても完全に隔絶されているわけではない。商館と平戸の街との一体感のようなものを感じた。きっとそれは江戸初期も同じだっただろう。今日訪れてみても、長崎以上に異文化がすぐ隣にあったことを感じとれる街だと思う。
街並み
ちょうどこの日は平戸くんち最終日だったようだ。昼間は少々観光客がいたのかもしれないが、夕方になると街はがらんとしていた。平戸は福岡から遠いため、観光客の引きも早いのだろう。日本海側ということもあって、日が傾くとなんとも言えない寂しさが際立った。
街並みは木造建築を主として歴史的景観を保とうという努力が感じられる。信州の中山道沿いの宿場町のような雰囲気がある。おくんち期間中だったのでどこの家も松浦家の家紋ののれんを掲げていた。長崎も同様におくんちの期間にはのれんを掲げるが、支配者の家紋ではなく自家の家紋入りののれんを掲げる。また長崎は一部木造建築の建物もあるが、大多数は近代的なコンクリート造や鉄骨造の建物3で、歴史的な景観というのはほとんど見られない。その点で長崎生まれの嫁さんは平戸の街の景観に感銘を受けていた。




感想
正味の滞在時間が 3 時間くらいしかなく、ほんのちょっとしかいられなかったが、平戸はとても味わい深い街だと思った。オランダ、ポルトガルとの交易の歴史では長崎の陰に隠れがちだが、最初にポルトガル船が往来するようになったのは平戸だし、オランダとの交易を最初に始めたのも平戸だった。その前の時代には松浦党や倭寇の歴史もある。世界史で習う台湾の偉人の鄭成功は平戸生まれで母親は平戸の人だ。隠れキリシタンの歴史もある。キリシタン関係でも長崎市が注目を集めがちだが、江戸期に隠れキリシタンとして信仰を続けたのは五島や平戸の人たちだった。歴史のほかにも、海の美しさが挙げられる。平戸西部にある人津久海水浴場や根獅子の浜海水浴場は沖縄の海と見まごうばかりの美しさだ。
九州に住んでいてまだ平戸を訪れたことがない人は是非一度訪ねてみて欲しい。九州の日本海・東シナ海側には南国のイメージと違った、独特の雰囲気がある。 2016 年の「今年行った場所」で書いた唐津とセットで行ってみることをおすすめします。
-
去年利用したときは無料だったが、 2020 年の春から有料化されていている。料金は高め。持ち込みテントで 4,500 円、タープも別料金を取られるみたい。これでは利用する人減りそう。 https://nakazekamp.com ↩
-
松浦氏は中世の海賊・水軍松浦党の子孫。海賊が最終的には戦国大名になった。 ↩
-
原爆で焼けたからではと思う人もいるかもしれないが、長崎で原爆が投下されたのは市北部の浦上のあたりで、室町時代から幕末にかけて貿易で栄えた長崎の中心部は原爆で大きな被害を受けておらず、歴史的な街並みを残そうと思えば残せたのに残さなかった、というのが長崎の実情。 ↩






![for 夏のハンモック泊 [AXESQUIN ウンカイ light] : 山に野に川に呑みに](https://portalshit.net/imageproxy/200/https://livedoor.blogimg.jp/potato_sp/imgs/9/7/97e139ac-s.jpg)