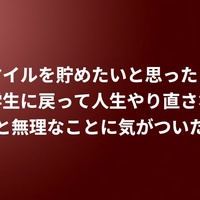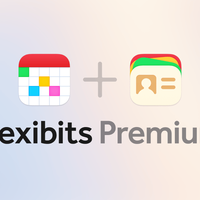マイルを貯めるのは低所得の自分には無理だという記事を書いた。
しかしこの記事を書いたあともセブンイレブンで 100 円のコーヒーを買うときもクレジットカードで払ったり、トイレットペーパーを LOHACO で買うときもポイントサイトを経由したり、通りすがりの自販機の釣り銭受けをまさぐって取り忘れの小銭をあさる中学生のようにちまちまマイルを貯め続け、なんとか家族三人そろって特典航空券(エコノミー)でホノルルまで行ける程度のマイルを貯めることができた。金持ちだと毎年ハワイにビジネスクラスで行けるくらいマイルが貯まるみたいだけど、自分の場合は 3 年かかってエコノミー(ローシーズン、 3 人分で 105,000 マイル)が限界だった。
なぜハワイなのか
2013 年に買った POPEYE がハワイ特集号で、「ハワイには若いうちに行こう」と書いてあった。自分はそのとき 32 歳で、コテコテのリゾート地に興味なかったのだけど POPEYE の特集を読んでみると「確かに良いな」と思えたので、なるべく年を取る前にハワイに行っておきたいなと思っていた。
ここ一年半くらい、身を粉にしながら働くものの大した成果を残すことができず、完全に人間として腐り始めていた。このままでは玄界灘で魚の餌になるくらいしか社会貢献の方法がないと思ったので、休みを取って旅行に行ってみることにした。
旅の準備

特典航空券界の常識をわかってなくて、マイルが貯まったらすぐに特典航空券を申し込めるのかと思っていたけどそういうわけではなさそうだった。マイルが貯まったので「来月旅行にでも行くか」とほくほくしながら特典航空券を申し込もうと ANA のサイトを覗いたら全然席が空いてない。ハワイのような人気路線の特典航空券は申し込めるようになった瞬間全部埋まってしまうみたいだった。 ANA の国際線の特典航空券の予約は 355 日前から可能になり、マイレージクラブのランクが高い人(= @t32k さんなどの金持ち)ほど申込みが優遇されるシステムなので、ランクの低いマイレージクラブ会員(=貧民)が特典航空券を申し込もうとしたらほぼ一年後の日付にするしかない。手持ちの一番古いマイルの有効期限が 2019 年の 2 月だったので、この時期に本当に旅行に行けるかどうかもわからないまま 2019 年の 2 月末に 2020 年 2 月のチケットを取った。申し込んだとき、どこに行くかとか何をするかとかどこに泊まるかとか何も考えられていなかった。やっと旅の予定を決め始めたのは 2020 年の正月だった。その後コロナウイルスの話が出てきて一旦は旅行を取りやめようかとも思ったが、先延ばしにすると逆に騒動が広がりそうだと思って予定通り 2 月中旬に出発した。

ハワイに行ってどうだったか
よかった。
カジュアル
ヨーロッパを旅行するときは結構緊張したが(人種差別とかマナーに気をつけたりで気をつかう)、ハワイは気楽でとてもよかった。
アメリカ人に対する良くないイメージが払拭できたのもよかった。少なくともハワイに住んでたりハワイに旅行に来てるアメリカ人からは、ヨーロッパの安宿で見かけるような声がでかくて何でもアメリカ流を押し通そうとする感じの悪さがなくて、嫌な気持ちになることなく旅行できた。
快適な移動
レンタカーや Uber 、 Lyft で移動したので移動で荷物を抱えて大変な目に遭ったり、タクシーにぼったくられないか心配したりしなくて済んだのが良かった。海外で車を運転するのは初めてだったが、ハワイの道は広くてとても運転しやすかった。
スーパークレジットカード社会
何でもカードで払えるので両替する必要がない。現金はチップを払うときか空港の自販機で飲み物を買うときくらいしか使う機会がない。 ABC ストア(ワイキキに 50m 間隔である旅行者向けのコンビニ)で現金で金払ってるのは日本人旅行者くらいだった。
eSIM 便利
今回は自分の iPhone 11 も嫁さんの iPhone XR も eSIM に対応していたので、香港の 3 というキャリアの eSIM を利用してハワイでも日本にいるとき同様に携帯が使えたのが良かった。 5 年前にギリシャに行ったときはちまちま Pocket WiFi をオンにしてインターネットにつないでいたので不自由極まりなかった。
ホテルの取り方
宿は Hotels.com と HIS で取った。 Hotels.com が最安かというとそういうわけではなく、マリオットなど結構良いホテルのチェーンだと HIS の方が料金安い&朝食付きだったりしてお得だった。
旅程
| 旅程 | 宿泊 | |
|---|---|---|
| Day 1 | 家 🚕 福岡 🛩 成田 ✈️ ホノルル 🛩 ヒロ | Hilo Hawaiian Hotel |
| Day 2 | ヒロ 🚙 アカカの滝 🚙 MKVIS | Hilo Hawaiian Hotel |
| Day 3 | ヒロ 🚙 ワイピオ渓谷 🚙 コナ | King Kamehameha's Kona Beach Hotel |
| Day 4 | コナ 🛩 ホノルル | Queen Kapiolani Hotel |
| Day 5 | ホノルル 🌴 | Queen Kapiolani Hotel |
| Day 6 | ホノルル 🚙 ノースショア | Queen Kapiolani Hotel |
| Day 7 | ホノルル ✈️ 成田 🛩 福岡 |
ハワイ島とオアフ島に三泊ずつした。福岡空港から成田へ行き、成田で 5 時間時間を潰してホノルルへ。ホノルルからハワイアン航空に乗り換えてハワイ島のヒロへ。ヒロに二泊してコナへ移動し、コナで一泊してからコナ空港からまたハワイアン航空でホノルルへ。なおコナではホテルにパスポートを忘れて大騒ぎとなったが、ハワイアン航空の職員の人がめっちゃ親切でスーパー助かった。ギリシャでエーゲ航空に散々な目に合わせられたのとは大違いだった。ホノルルに三泊して成田経由で福岡に戻った。 6 泊 8 日の旅(一泊は飛行機の中)。
ハワイ島

ハワイ島ではアカカの滝、マウナケア(中腹まで)、ワイピオ渓谷、コナブリュワリーの工場レストランなどを訪れた。主にレンタカーでドライブしていて、ハワイ島の北半分をぐるっと回った。



ハワイ島はハワイ諸島の中では一番新しい島でまだ火山の荒々しい感じが残ってる。マウナケアは 4200m もある高い山だが、裾野が広がっていて草原が広がり、景色が生まれ故郷の阿蘇に似ていて海外旅行に来てるのに帰省してるみたいな感じで不思議な感覚だった。

オアフ島
オアフ島ではワイキキに滞在しつつ、ビーチで遊んだり、街をうろついたりした。

オアフ島でも一日は車で遠出して、ノースショアまで行ってパタゴニアで環境に配慮しながら家族で爆買いしたりした。


ダイアモンドヘッドが見える宿に泊まっていて、できれば登りに行ってみたいと思っていたけどうだうだ無為に時間を過ごしてしまってついぞ登ることができなかった。残念。

ワイキキは福岡でいうと西通りといった趣でひたすらショッピングするのが好きな人にはよさそうだが少々退屈だった。ライドシェアの Lyft で、カカアコという昔は治安が悪かったけど最近は小洒落た店が増えているエリアに行ってオシャンティなレストランでラム肉を食べたりした。

POPEYE で紹介されていた Ray's Cafe という店が安くて巨大なリブアイやロブスターが食べられるようだったが、治安の悪いエリアにある地元民向けのレストランのようで閉店時間が早く、今回は行くことができなかった。
旅行中のツイート
福岡市西区のハワイからハワイの今宿に来ました。 pic.twitter.com/SCj3bk4iwF
— morygonzalez (@morygonzalez) February 9, 2020
正直、ハワイは一回行けば充分だろうと思っていたが、旅行から帰ってきてからは「またハワイに行きたい」という気持ちが日々募っていく一方だ。酒のやまやに行ってコナビールやフラ印のポテトチップスを買ったり、中公新書のハワイの歴史についての本を読んだり、Amazon Prime ビデオで HAWAII FIVE-0 というドラマを見たりしている。
HAWAII FIVE-0 ではよく主人公が山登りに行っている。ハワイといえば海というイメージあるけど、ダイヤモンドヘッド以外でも登り甲斐のありそうな山がたくさんある。今度は山に登ったり、地元民向けの治安が悪いエリアの店にも乱入してみたりしたい。

それにつけても金の欲しさよ。