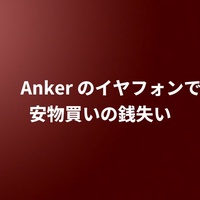具合が悪いときにテレ東の廃墟の休日が見たくなってどこでやってるか探したころ Hulu にあると Google の検索結果に出たので Hulu に入ったが、なんと不運なことにすでに Hulu での配信は終了しており見ることができなかった。

ドラマ名で Google 検索するとアフィリエイトサイトがいっぱいヒットして「○×は Hulu で見られる?」みたいな記事ばかり検索結果に表示されて地獄みがある。 Google の↑みたいな表示は便利だけど常に最新の情報だとは限らないみたい。
そんで代わりに何か見られるものはないかと物色していると、ダミアン・ルイスが出ているドラマ HOMELAND があったので見始めたところ、かなり面白い。
ダミアン・ルイスは HBO の『バンド・オブ・ブラザース』で主人公のリチャード・ウィンターズを好演しており、好きな俳優だった。バンド・オブ・ブラザースでは少佐まで昇進したあと少尉時代に自分をいじめていた元上官(大尉)とすれ違うときに、自分のことを無視して通り過ぎようとしたのを呼び止めて敬礼させるシーンがとにかく良い。
We salute the rank, not the man.
HOMELAND は時代を現代に移しているが、ダミアン・ルイスは同じ軍人役で登場している。ただバンド・オブ・ブラザースのときと違ってとにかくかっこよい理想のヒーローとは異なり、ダークなヒーローを演じている。イラク戦争でアルカイダの捕虜になり、 8 年ぶりに救出された海兵隊員の話。帰還してマスコミにちやほやされヒーローのように取り扱われているが、アルカイダに洗脳されていてテロリストに転向したのではないか、というもの。イスラエルのドラマのプロットを借りてアメリカで作り直したものらしい。
人のパソコンや携帯に入り込んで何でも監視したり盗聴したりしててさすがにそこまではできないのではという感じなんだけど(ターミナル風の黒い画面でカチャカチャターンとやると何でもできる)、スノーデン事件なんかを見る限り CIA やアメリカの諜報機関はああいうことをやっているのかもしれない。
全部でシーズン 7 まであって、 4 以降はダミアン・ルイスは出てこなくなり、話の舞台もアメリカからパキスタンやヨーロッパに移るが、アルカイダやシリア動乱などを反映しており中東をはじめとした世界情勢の復習になる。その点でアメリカ国内に閉じて話が進む Netflix の House of Cards よりも話に広がりがあって面白い