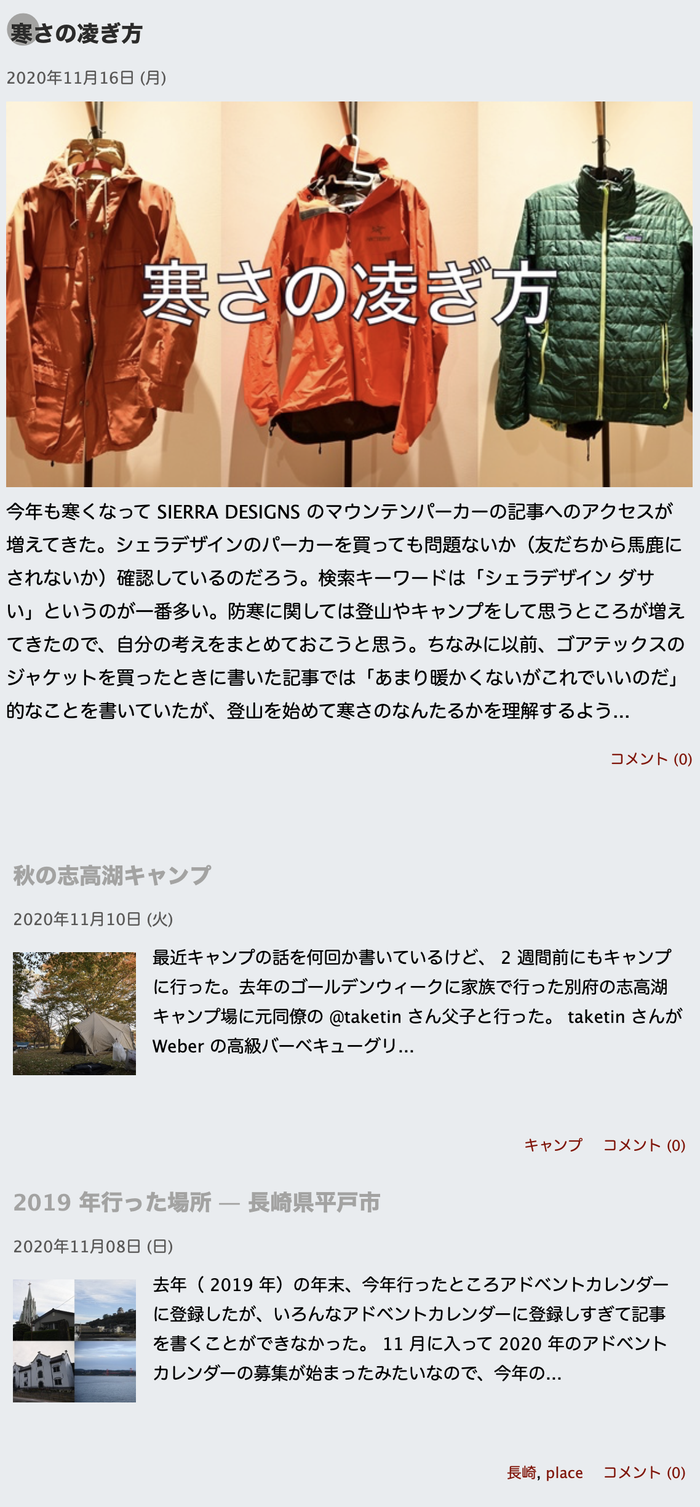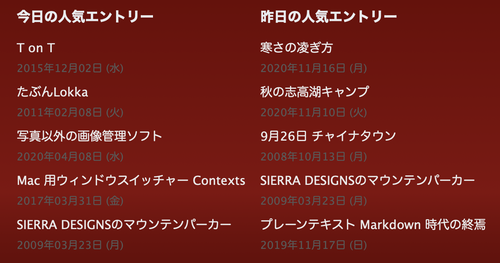"Your Computer Isn't Yours" という記事が先週バズってた。
概略を説明すると、 Catalina の頃から Apple が Mac ユーザーのアプリ起動ログを勝手に収集していたが、 Big Sur の公開日にログ集約サーバーがダウンしてしまい、そのせいで Mac を使えなくなる人が続出して問題が発覚したというもの。 Rebuild の Episode 288 で触れられているので興味がある人は聞いて下さい。
この記事については日本語の翻訳もあってはてブで 500 ブックマークくらいついていたが、どうも機械翻訳されただけのようだったし、一部訳が違うのではと思われるところがあったので自分でも訳してみた。訳を原著者の Jeffrey Paul 氏にメールで送ったので恐らくそのうち本家に日本語訳が追加されると思う。

2020-11-25 9:16 追記
日本語訳追加してもらいました。
起きていることをまとめると以下のような感じだ。
- Apple は Mac ユーザーのアプリ起動データを IP 付きで Apple のサーバーに集めている(ログ送信)
- 各アプリの署名有効期限チェックやマルウェア対策のためということになっている
- Mac から Apple への通信は暗号化されていない
- ISP や CDN ( Akamai )、ネットワークを盗聴している他人が内容を確認可能
- この通信はユーザーが自分の意思で無効化できない(「Mac解析を共有」をオフにしても送信される)
- Mac (特に Big Sur でしか動かない Apple Silicon Mac )を使いたければ利用ログ送信を甘受するしかない
- Big Sur から、上述のログ送信や Apple 製のアプリは VPN やファイヤウォールを無視するようになった
- OS の挙動を変更しようとすると Mac が起動しなくなる
- iCloud Backup は iMessage の秘密鍵も一緒にバックアップするので Apple がメッセージの内容を読むことができる
- 自分自身が iCloud Backup 利用していなくても、メッセージの送信相手が iCloud Backup を使っていると自分が送ったメッセージが iCloud 上に保存される
-
Apple はプライバシー保護を売りにしながらユーザープライバシーをなおざりにしている
- iMessages/iCloud Backup のバックドアを放置している
- 過去にアプリ開発者には HTTPS を強制しながら自分たちは OCSP の通信を平文で行っている
- ログ送信の件について対応を発表したが、対応時期を明確にしていない
その結果、以下のような状況に陥ることが懸念されている。
- Apple が集めている情報は NSA や FBI に筒抜けになる
- Apple はアメリカ軍の諜報機関や FBI にユーザーログデータなどの閲覧を令状なしで認める協定を結んでいる
- iCloud Photo や iMessage の内容を Apple だけでなく軍や FBI も見られるようになっている
- ユーザー保護を隠れ蓑に Apple が力を増大させる
- マルウェアから守る、を大義名分にして、ユーザーがどのアプリを動かせるかを Apple がコントロールできる可能性がある
- 原理的には Apple が気に入らないアプリを起動できなくしてしまうことが可能
モバイルアプリの利用状況の収集は多分いろんなアプリがやっている。 Mac で Apple が集めている程度以上の情報を集めているアプリも多いだろう(位置情報を取得しているアプリなど)。なので最初この件については過剰に反応しすぎなのではないかと思っていたが、よくよく考えてみると自分の感覚の方が麻痺していたのかもしれない。アプリの利用履歴を IP アドレス付きで送るということは、どこで何をしているかがアプリ開発者に筒抜けだ。そしてそのログを公権力が自由に閲覧可能だとしたらいい気持ちはしない。
アプリと Apple の場合で決定的に異なるのは、アプリはそのアプリが起動している間(あるいはバックグラウンドでのログ送信を許可されている間)だけログを送信するが、 Mac に関して言うとずっーっと起動しっぱなしで使い続けるものなので、ログデータからユーザーの行動履歴・生活様式がわかってしまう。地図アプリで検索した場所の情報も送られていたということなので、 Jeffrey Paul 氏が書いているように、その人がこれから行く予定の場所もわかってしまう。
GDPR や様々なプライバシー保護は、アプリを作りサービスを運営する側としては正直厳しいなと思うところはあるけど、 Apple がアメリカ軍と結んでいる PRISM のような取り決めが存在すると、様々な個人情報が政府機関に流れてしまって、アメリカのサスペンスドラマのように個人の位置情報を携帯の使用履歴からいとも簡単に割り出せるようになってしまう。それはやはり恐ろしい世界だ。
プライバシーの侵害のみならず、プラットフォーマーである Apple の匙加減次第で、ユーザーが使えるアプリが決まるという状況も好ましくない。たびたび iOS の App Store で起こる Apple の恣意的な審査基準改変などはその一端だ。 Hey の件で Apple とやり合った DHH は痛烈に Apple を批判するとともに、かつて邪悪な Microsoft に対抗するための救いとも言えた Apple が以前の Microsoft 以上に邪悪になってしまったのが嘆かわしいと Twitter に書いていた。学生の頃、 Mac を広める活動をやって大学のクラスの半分の同級生のラップトップを Mac にしたというエピソードや、 Rails の開発でも Mac を激推ししたという話は胸熱だった。応援してきた Apple が Evil になってしまい、人一倍残念に思っているのだろう。
That's a formative experience! To have Apple be the escape pod from Microsoft and Windows. I spent so much effort in the early days evangelizing them because of that. Converted half my university class to Macs. Pushed it hard with Ruby on Rails. Team Apple through and through.
— DHH (@dhh) November 18, 2020
Apple はかつて "The computer for the rest of us" というコピーで Macintosh を宣伝していた。しかし今日、 Mac は彼らのコンピューターになってしまったのだ。