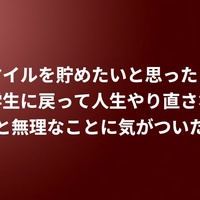外出自粛かつ自分自身にコロ助疑惑があったのでずっと部屋に閉じこもってサイトのデザインをいじってた。

上がこれまでで、左下が今後、右下が画像がワイドな場合のバージョン。これまで横幅 1280px 想定にして画像も横幅 1280px のサイズで表示するようにしていた。
ただしこれだと写真は見やすくても文字が読みにくい。人間の目は 1280px 繰り返し左右に移動させるのには適していないようだった( N=1 )。
そういうわけでまたまた cho45 さんのブログのレイアウトをパクって、文章は横幅短めに、写真はでかいサイズで表示するようにした。
文章部分の幅を 800px にして、画像を読み込んだときに一定の条件にマッチしたら写真の横幅を 1280px で表示するようにした。 margin-left: -250px; してるのがミソ。横幅 800px だと大分文章は読みやすいし、でかい写真は大きく見えて便利。
@media screen and (min-width: 1422px) {
#content #main article .body > p {
img[class~="large"] {
width: $content-max-width;
max-width: $content-max-width;
margin-left: -250px;
}
}
}JS はこんな感じのコードを書いた。
const checkImageSize = (target) => {
if (typeof target === 'undefined') {
return;
}
const width = target.naturalWidth;
const height = target.naturalHeight;
const isPhoto = RegExp('(lh3\.googleusercontent\.com|\.jpe?g$)').test(target.src);
if (width > 1279 && width > height && isPhoto) {
target.classList.add('large');
}
}
const lazyImageObserver = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
entries.forEach(entry => {
if (entry.isIntersecting) {
const lazyImage = entry.target;
lazyImage.src = lazyImage.dataset.src;
lazyImage.addEventListener('load', (event) => checkImageSize(event.target));
lazyImageObserver.unobserve(lazyImage);
}
});
});
const selectors = "#content article .body img, #content article .similar img";
const lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll(selectors));
if ("IntersectionObserver" in window) {
for (let image of lazyImages) {
const src = image.src;
image.dataset.src = src;
if (lazyImages.indexOf(image) === 0) {
const promise = new Promise(resolve => resolve(image));
promise.then(checkImageSize).catch(setTimeout(checkImageSize, 100))
continue;
}
image.src = "";
};
lazyImages.forEach(lazyImage => {
lazyImageObserver.observe(lazyImage);
});
}画像の読み込みが起こったタイミングにフックして画像のサイズチェックを行い、条件にマッチしたら img タグに class を追加し、 CSS のメディアクエリと合わせ技で大きく表示するようにしている。以前やった画像の遅延読み込みのコードを改良した。
その他、 HTML 5 対応が中途半端だったのでマークアップを見直して、適度に <header> や <secition> 、 <article> 、 <footer> を使ってマークアップし直した。 このせいだと思うけど Google Adsense の自動広告が差し込まれる位置が変わった。これまでヘッダーの下に入り込んでいたやつが <header> と <article> の間に入るようになった。
今後も外出禁止が続いたらひたすら自分のブログをいじってしまう予感。こういうエネルギーを仕事とか個人サービス開発とかに当てられるとよいのだろうけどなかなかそういう方向には向かない。