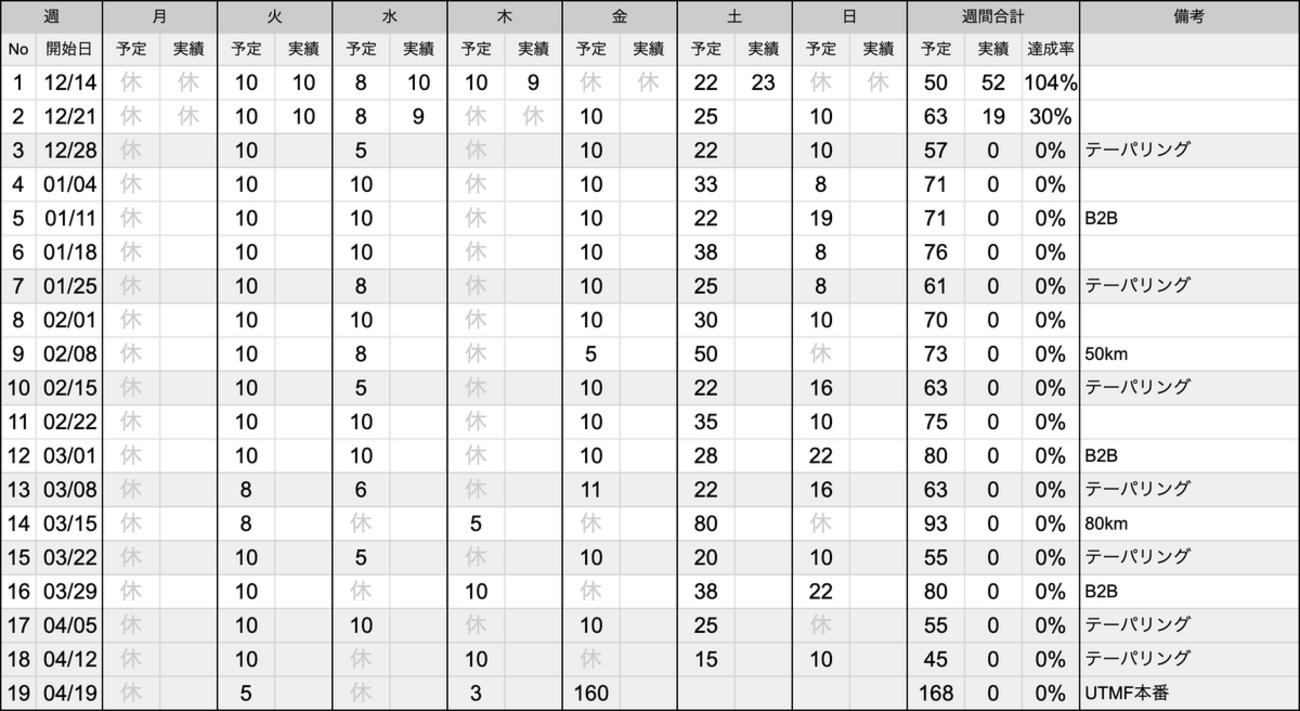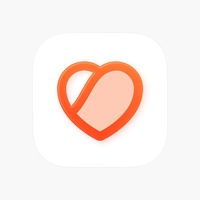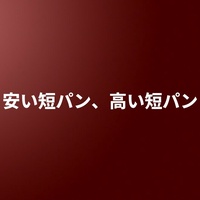サウナイキタイのサ活と Google マップのクチコミには結構乖離があることに気が付いた。自分が行ってめっちゃ気に入って、サウナイキタイでも好意的なサ活が多い佐賀の KOMOREBI の評価が Google マップでは低い。サウナにも水風呂にも入らないのに物価の安い九州(温泉に 500 円で入れる)で風呂に 1100 円払えと言われたら高すぎると感じる人もいるのだろう。しかも混んでるし。
Google マップのクチコミはとても便利だけど、一つの施設で二つ以上の役務を果たしてる場所や客を選ぶタイプの店は評価が下がると思う。本当は自分の好みにピッタリの施設が低評価となっている可能性がある。なので評価が低いからと切り捨ててしまうのではなく、自分と似た属性の人からのクチコミを探し出して読むと実際のところの雰囲気がわかるかもしれないが、それは難易度が高すぎる。
今日のプラットフォームサービスには不幸なマッチングを回避する仕組みが必要なのだと思う。あなたはサウナ好きだからこの施設は満足できますよとか、ここは常連向けですよ的な情報が簡単にわかるようになるとか。
ただ一方でそれは Instagram で自分のようなおっさんに微エロのリール動画ばかり表示されるようなレコメンデーションとアルゴリズムによる支配がいろんなサービスに広まるということであり、それはそれで残念ではある。
インスタグラムのホームに差し込れたり検索タブでお薦めされるリール、おっぱいがボヨヨンとしてるような微エロなやつが多い。「お前は禿げで愚鈍な中年おやじだからこういうエロっぽいのが好きなんだろ?」と言われてるみたいで嫌な気持ちになる。 pic.twitter.com/YTWxm7xdj0
— morygonzalez (@morygonzalez) April 23, 2022
40代おじさんの集まりに行ったら、インスタグラムでおっぱいボヨヨンか小動物の動画ばかりおすすめされて腹が立つ、機械学習とか使ってもこんな偏見まみれのレコメンドしかできんのか、ホェースブックはよ潰れてほしい、という話で盛り上がった。
— morygonzalez (@morygonzalez) August 5, 2022
もう一つの選択肢としては、釣り SNS や登山 SNS が出来たように、レビューサイトも専門分化させていくアプローチが考えられる。自分のようなアルゴリズムやレコメンデーションにあらがいたいウェブ縄文人にはそういう進化の方が向いているかもしれない。
というようなことを思ってたら一つ前の記事に言及しつつ伊藤直也さんが似たようなことを書いていた。
最近のはしらないけどかつての2ちゃんねるとか Reddit とかは、ある程度の規模のコミュニティが、大きくなってくると自然に分割されて分散されていく構造を持っていて、これはいいなと思っていた
— naoya (@naoya_ito) January 16, 2023
2ch みたいにごちゃごちゃカテゴリーがサイドバーに並んでいるのには普通の人には難しすぎるので、釣り掲示板がツリバカメラになり、登山掲示板がヤマレコや YAMAP になったんだろう。考えてみるとサウナイキタイもサウナに特化した SNS ・情報サイトだ。
サウナイキタイに話を戻すと、サウナイキタイはローカルルール満載の町銭湯に対する評価が甘いという特徴もある。サウナイキタイでベタ褒めされてる施設(「番台のおばあちゃんが優しい」、「常連の方達とほのぼの交流」などなど)が Google マップではボロクソに書かれてたりする(「番台は意地悪ばあさんそのもの」、「彫り物を入れたヤクザや半グレの常連でサウナが占有されていて入れない」などなど)。ネガティブなことは書かないというコミュニティポリシーの影響なんだろうか(以前、サ活でドラクエ集団がいたと書いたら公式アカウントから警告された)。サウナイキタイだけ見て福岡の銭湯サウナに行ったら刺青を彫った怖い人から凄まれながら入浴しなければならないという体験をしそうだ。
レコメンデーションにしても専門分化にしても塩梅が難しい。レコメンデーションはやり過ぎるとただの偏見にしかならない( 40 代男性はおっさん → おっさんはエロが好き → 微エロ動画見せとくか)し、専門分化して蛸壺化しすぎると一般的な感覚と離れたレビューが集まるようになってしまう(怖い人だらけの銭湯サウナが高評価)。昔のインターネットではこんなことに悩むことはなかった。
昔のインターネットは良かったとばかり言ってもどうにもならないが、インターネットを飯の種とする者の一人として人が増えたいまのインターネット特有の問題をどうにかしたい。