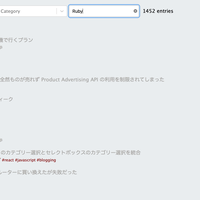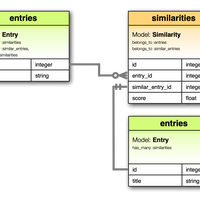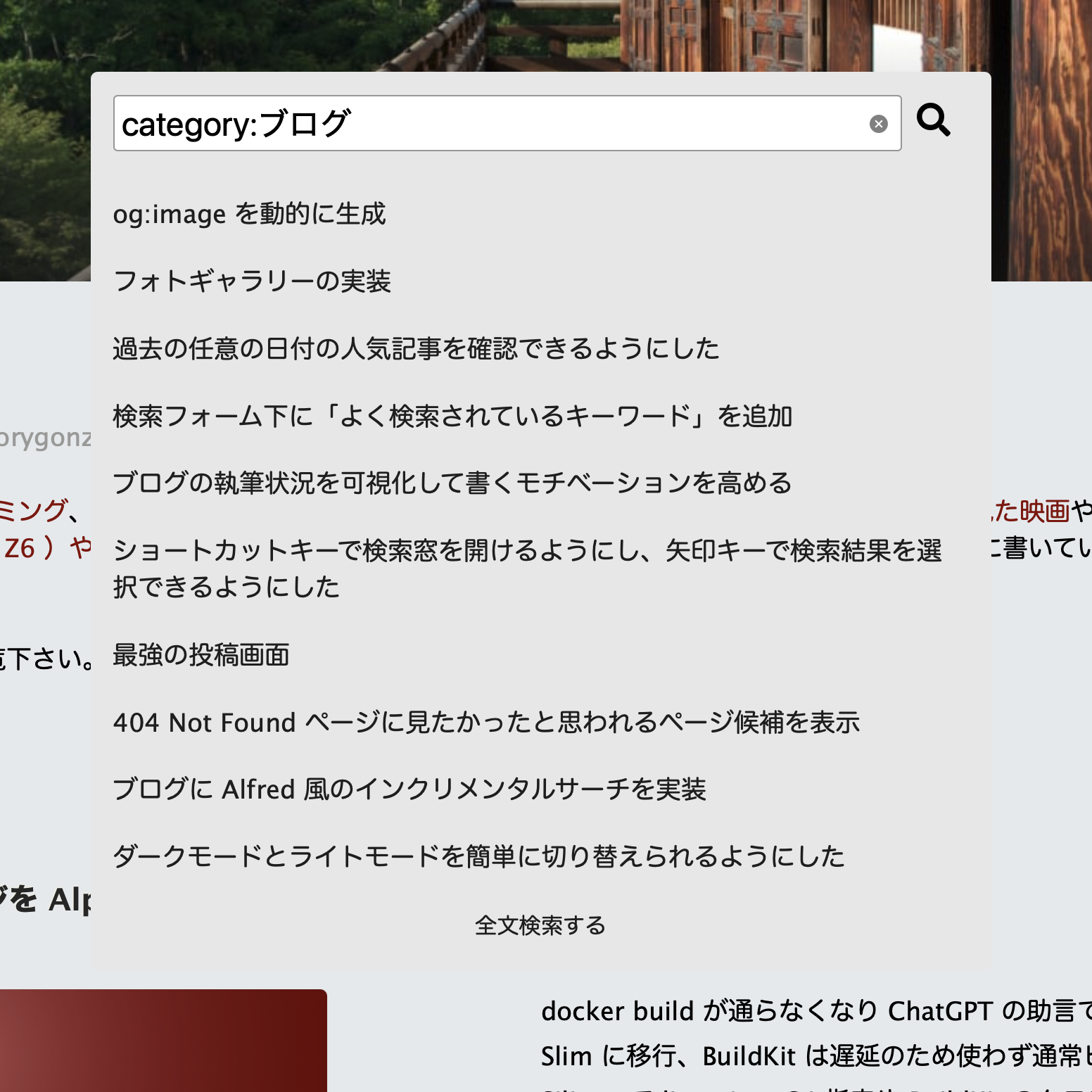
ふと思い立ってカテゴリーで検索できるようにしたら便利だろうと改修してみた。 Tantiny には facet_query というものがあって、カテゴリー名などは検索インデックスの型を facet にしておくと、カテゴリーだけを検索対象にできる。実装してみたところ便利。カテゴリー内の記事一覧ページを表示する機能はあるが、本文やコメントなども読み込むため遅い。タイトルだけ一覧でがっと欲しいときにカテゴリー検索は便利。
同様にタグでも検索できるようにしてみた。こちらは term_query を使っている。本文の検索は検索キーワードを形態素解析してトークナイズされた文字列で検索しているが、タグ名での検索は exact match をするようにしている。なので過不足あればヒットしない。完全一致で検索したいときに便利。
ただ、これまで記事にタグを設定してこなかったのでタグ未設定の記事が多い。ということで ChatGPT に記事の内容を読ませてタグを自動生成してもらうようにした。ちょっとへんちくりんなタグを設定することもあるが、文脈を読んでタグを設定してくれる。本文中にキーワードはないけど記事の内容に合致するタグを選んできたりもする。賢い。
ちなみに今回 ChatGPT のモデルを gpt-4o から gpt-5-mini に変更した。 GPT 5 系に移行するためには Chat API から Responses API への移行が必要だった。最初それがわからず難儀したが、 Responses API の方がパラメーターがシンプルで使いやすい。例えば JSON のフォーマットを指定したいとき、 Chat API だと JSON Schema で定義を書いて渡す必要があったが、 Response API であればプロンプト中に「こういうフォーマットでくれ」と書けばそのフォーマットで返してくれる。すごい。
require 'openai'
class EntryTagGenerator
MODEL = 'gpt-5-mini'
PROMPT = <<~EOF
添付のブログ記事に関して、文章の内容を反映したタグを付与してください。ただし、以下の条件を遵守してください。
1. ブログ全体のタグの一覧は「 %s 」です。ふさわしいものがあればそこから利用してください。なければ新しいタグを考えて設定してください。
2. タグの数は最大で 5 個までとします。
3. すでにタグが付与されている場合は、現在のタグを加味して 5 個までタグを付与してください。現在のタグが内容にふさわしくなければ削除しても構いません。
4. タグは極力一語で構成されるようにしてください。固有名詞の場合はその限りではありません。
5. 略語は避けてください。固有名詞の場合はその限りではありません。
6. 「減量ダイエット」のような意味が重複する二つの単語で構成されるタグは付与しないでください。固有名詞の場合はその限りではありません。
7. タグは半角スペースを含んでも問題ありません。"GoogleAnalytics" ではなく "Google Analytics" でよいです。
8. レスポンスは JSON フォーマットで、以下のような形式にしてください。
\```json
{
"tags": ["tag1", "tag2"...]
}
\```
# ブログ記事 #
## タイトル ##
%s
## 本文
%s
## すでに付与済みのタグ
%s
EOF
attr_reader :response
def initialize(title, body, tags)
@title = title
@body = body
@tags = tags
@client = OpenAI::Client.new(access_token: ENV['OPENAI_API_KEY'])
end
def generate
@response ||= begin
request = @client.responses.create(
parameters: {
model: MODEL,
input: input,
reasoning: { effort: 'minimal' }
}
)
JSON.parse(request.dig("output", 1, "content", 0, "text").strip)
rescue => e
puts "タグ生成エラー: #{e.message}"
nil
end
end
def input
PROMPT % [Tag.joins(:entries).pluck(:name), @title, @body, @tags]
end
end