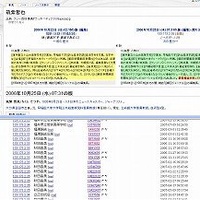低音が割れる状態が続いていたゴルフのフロントスピーカーを取り外して修理しました。以前、リアスピーカーは修理していたので(スピーカーDIYリペア、ワイパーゴム交換)、同じ手順でやってみました。正直、満足の得られる音質ではないですが、ずいぶんマシになりました。
ところで今回、作業工程の写真を撮ってアップすべきかなぁと思いましたが、ついついおっくうでさぼってしまいました。しかしさぼるべきではなかった。作業後、前回修理したときに参考にしたWoodmanという方のウェブサイトを訪れてみたら、サイト自体がなくなっていました。また、ソニーモバイル内でゴルフ2やジェッタのオーディオ関係のフィッティング情報が公開されていたのですが、こちらも消えてなくなっていました。
シートのワイヤーが一本切れただけで手に負えなくなるような状態のゴルフ2。長く乗りたいのなら、数少ない乗り手の一人としてもっとメンテナンス情報などは公開していくべきだなと反省した次第です。情けは人のためならず(ちょっと違うかな?)