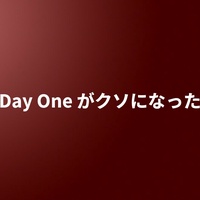女性のブログのコメント欄で本文と関係ない自分の近況などを書くおっさんマジで恐怖
— morygonzalez (@morygonzalez) August 23, 2020
最近時々見るようになったあるブログ(ブログ主は女性)のコメント欄で、すべての記事に必ずコメントしているおっさんがいるのに気がついた。本文の内容と関係あるコメントをすることもあるが、大抵は本文と関係ないか関係あってもほんのちょびっとかすってるだけの自分語りだ。
例えばブログ主が「今日は温泉に行ってきました〜」と書けば、コメント欄に「うちの姉から柿が届きました」というような投稿をする感じ。ブログ主は律儀に返信しているが、第三者の自分が見ても恐怖を覚えるくらいの脈絡のなさ。
一時期おっさんの自分語り LINE みたいなのが Twitter で話題になった。相手の事情など考えず、自分が言いたいことを強引に送ってきたりするのがおっさん LINE の不快感の原因だと思う。
しかしよくよく考えてみると自分も 20 年くらい前はこういうコミュニケーションをしていた気がする。なぜこういうことになるのかというと、むかしはスマートフォンもなく、インターネットでのコミュニケーションにはタイムラグがあったからだと思う。掲示板やブログのコメント欄でのやりとりは非同期なので、やりとりの一往復にとても時間がかかる。すると相手が何を言うかをある程度推測して長めの文章を投稿したり、酷い場合には多少オフトピック気味な自分語り的な投稿をしてしまうことがあった気がする。
今日では誰もがスマートフォンを持ち、ブログへのコメントの返信は一々パソコンを立ち上げなくてもスマートフォンからさっと行うことができる。そもそもブログでコメントするという行為自体が前時代的で、コミュニケーションの大半の部分が Twitter や Instagram 、 Facebook など SNS 上で行われている。そしてそのやりとりはもっとクイックで、コミュニケーションの一往復にかかる時間は短く、一回あたりの情報量はコンパクトになってきている。
きっと他人のブログのコメント欄で自分語りおじさんは 20 年以上前のインターネット黎明期にインターネットを始め、そのときのインターネット仕草が身にしみてるのだろう。 Twitter や Facebook にも馴染むことができず、 20 年前と同じ自分語りを他人の空間で行ってしまうのではないだろうか。そういうおっさんにはなりたくない。