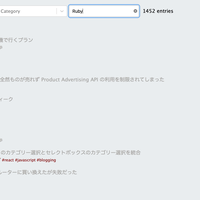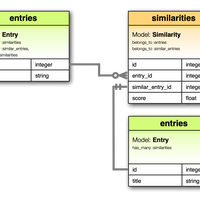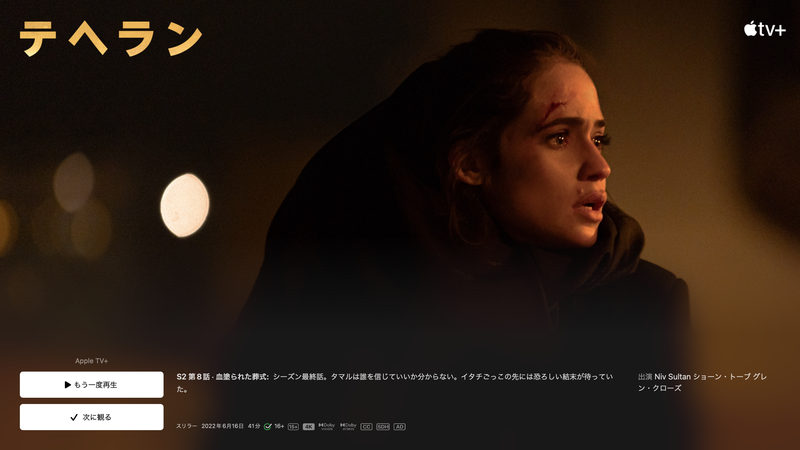
5 月からテヘランシーズン 2 が毎週 1 エピソードずつ公開されてて毎週楽しみに見てた。 Homeland もだけど、自分はどうもイランが絡むスパイものドラマが好きみたいだ。テヘランは面白かったが最後の終わり方が何それ感があった。あれでシーズン 3 なかったら納得がいかない。ショーン・トーブももっと活躍して欲しい。シーズン 3 が作られて欲しいので Apple TV+ に入ってる人は見てください。

コロナに罹患してスーパー具合が悪いときにザ・モーニングショーを一気見した。いわゆる #MeToo 的な内容だが、主人公アレックス・レヴィ役のジェニファー・アニストンが 50 代とは思えぬ美しさで輝いていた。ミッチ・ケスラー役のスティーブ・カレルも中年男性の魅力を遺憾なく発揮していて良かった。同じ人物が「40歳の童貞男」の主人公を演じているとは思えないかっこよさだった。
#MeToo 的な話は映画業界などを中心に最近日本でも問題になっていたが、ザ・モーニングショーで取り上げられているのはもうちょい悪質度が低い問題な気がする。いわゆる飲み会でお持ち帰りした的なやつだ。多分裁判したら女性の方は勝てない気がする。少なくともいまの日本では。女性の方が抵抗しなかったという意味で合意の上での出来事っぽいんだけど、いまのアメリカのリベラルな基準で言うとそれはアウトで、男性側は社会的に抹殺されるようだ。そう遠くない将来に日本でもそういう空気感に変わっていくのかも知れない。村上春樹のノルウェイの森に出てくる永沢さんなんかは外務省クビになると思う。プレイボーイの人はザ・モーニングショーを見て認識を改めた方が良さげ。
Apple TV+ 、テッド・ラッソはじめカバー写真が惹かれなくてなかなか見てこなかったけど、見始めると面白い。次はフォー・オール・マンカインドを見たい。